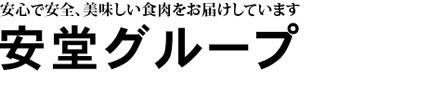安堂グループの歴史物語[第7話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第7話
注文が来ても、売るものがない
高度経済成長の真っただ中の昭和40年代、日本人の食卓にも大きな変化が訪れていました。その最たるものに牛肉の普及があります。
急増する牛肉需要に応えるため、畜産業や食肉卸業にも変化が求められていました。
取引は増えたが…
弟・繁美によるドライブインの成功の裏で、親之は地道な努力を重ねていました。ドライブイン開業の5年前の昭和35年頃、小学生だった安堂光明(現会長)は、父・親之が毎朝、地元・周東町のこーべや精肉店に半頭分の正肉(骨や余分な脂肪をとった肉)を配達する姿を覚えています。こーべや精肉店は後にミニスーパーを開業、小さな売場ながらも驚異的な売上を記録する繁盛店へと成長しました。
また、遠く宇部市の小売店へも正肉を蒸気機関車に載せて運ぶようになりました。そのうちオート三輪(三輪トラック)を購入すると、親之や繁美が悪路を運転して肉を届けるようになりました。
ある時、配達を終えた帰り道、オート三輪が突然故障して立ち往生したことがありました。現在のように、自動車整備のレスキューなどない時代、整備工場へ持ち込むこともできません。明日にはまた配達が控えています。しかも、同じ地域の同業他社からの配達依頼も受けていました。当時は、配達の方面別に同業者が協同して配達を担っていたのです。
ほとほと困った親之は、驚きの行動にでました。中古のオート三輪を見つけると、なんとその場で購入し、その日の内に帰ってきたのでした。
やがて国道2号線の道路事情が改善されると、四輪のトラックが活躍するようになりました。その運転を任されたのは、親之の妻・都子(みやこ)です。運転手を雇う余裕はなく、苦肉の策でした。
当時はまだ運転免許を持つ者は少なく、女性ドライバーなど聞いたことがないような時代です。「なんで女が免許をとらんにゃあいけんのか!」と姑のユキが愚痴をこぼしたのも当然でした。都子は急いで免許を取ると、毎日のようにトラックに乗り込み、ユキは道中の安全を祈るしかありませんでした。
車が故障しようが、体の調子が悪かろうが、男女の隔てもなく、明日の注文のためにはどんな困難も乗り越える。そんな商いの姿勢が客からの信頼となり、折からの牛肉の需要増もあって、取引はどんどん増えていきました。
ところが、それを手放しで喜ぶことはできませんでした。商品を納めようにも、肉が確保できないのです。そもそも、肉牛の素になる牛(素牛・もとうし、生後6~12ヶ月くらいの仔牛)が全国的に不足していました。
牛を探して右往左往
親之が考案して農協が導入した農家への肥育預託制度によって、肉牛の安定供給が実現するはずでした。実際に昭和43年末、農協が契約する農家は23戸、常時400頭ほどの肥育が行われていたことが記録されています。
しかし、それだけでは旺盛な牛肉需要を賄うことができなくなっていました。昭和40年代半ばを過ぎて、日本人の食事事情は劇的に変化し、スーパーマーケットが躍進していました。
牛肉の卸売業者は牛を求めて、各地の市場を渡り歩くようになりました。すぐに商品化できる肉牛はもちろん、これから肥育する素牛を求めて、地元の市場から市場へ、そしてよりたくさんの牛が集まる大規模な市場へ…。
かつて日本一の取引量を誇ったのは、尾道家畜市場(広島県尾道市)でした。やがてその活況は、牛の産地により近い高梁家畜市場(岡山県高梁市)へと移ります。さらには、三次家畜市場(広島県三次市)が、山陰からも牛を集めて活況を呈するようになりました。安堂商店もまた、中国地方はもちろん、九州にも素牛を求めるようになりました。
「注文は増えたのに、届ける肉がない。育てる牛もいない」。
親之はどうしようもないもどかしさに苛まれていました。

▲昭和50年代ごろの高梁家畜市場の様子
写真提供:JAびほく
千載一遇のチャンス
そんなある日、チャンスは突然にやってきました。
取引先の一つだったスーパー・ユニードの本部(福岡市)へ納入に訪れていた親之は、ある噂を耳にします。
「おい、かなりの頭数が今度、売りに出されるらしいよ。でも、ちょっと訳ありみたいでね。会社は仕入れるのを諦めたよ」。
すぐにスーパーの役員に問い合わせると、その牛はある企業が投資目的で肥育していた牛だとわかりました。その牛を急いで現金にしなければならないある事情ができたのだというのです。
スーパー・ユニードといえば、明治28年創業の老舗。博多の呉服屋に始まり百貨店となり、当時はスーパーマーケットを九州や中国地方に展開し、消費者から絶大な信頼を得ていました。肉牛は喉から手が出るほど欲しいユニードですが、後で問題になるかもしれない取引に、手を出すわけにはいきません。
さらに、加工後の正肉の取引には慣れていますが、生きた牛で、まだ肥育が必要な素牛もいると聞いて、尻込みをしていました。素牛の取引では、その姿だけで値を決める目利きの能力が不可欠です。スーパーにはそれができる社員はいません。
「その取引、わしにやらせてくれないか」。
それは、慎重派の親之の口から発せられた思いがけない言葉でした。一体、何頭いるのかわからないが、素牛を欲しがる農家はいくらでも手配できる。値付けの目利きも日常のこと。そして何よりも、牛が手に入るとなれば、居ても立ってもいられなかったのです。
早速、教えてもらった人物に連絡を取ると、すぐに名古屋へ牛を引き取りに行ってくれとのこと。その名古屋で、親之は生涯忘れない光景を目の当たりにすることになります。数えきれないほどの若い牛たちの群れです。鼻輪(鼻環)さえつけられていない牛たちが、元気に走り回っていたのです。