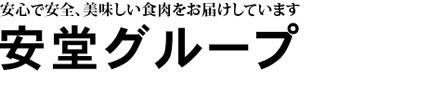安堂グループの歴史物語[第2話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第2話
試行錯誤、安堂商店の黎明期
終戦から2年が過ぎた昭和22年(1947)、世の中がまだ混乱していた時期に安堂商店は生まれました。店主の安堂寿(当時、42才)とユキ夫婦、そして息子・親之(21)は、家畜商で食べて行こうと、がむしゃらに働きます。誰もが、生きることに必死だった。そんな時代でした。
後発組として辛酸をなめる
高森地区は明治期から食肉産業の盛んな地域です。戦後に開業した安堂商店は最後発の新参者。何をするにしても、不利な状況でした。苦労してやっと牛肉を精肉店に納める仕事がとれても、屠畜場を使わせてもらえる順番は、他の業者が使い終わった最後でした。
寿の孫であり、親之の長男、後の三代目になる現会長・安堂光明(昭和27~、1952~)は、屠畜場で使った道具を丁寧に洗う寿の姿を憶えています。米俵を両手にそれぞれ抱えるほどの怪力の持ち主だった寿が、翌日の作業のために道具を洗う姿、そして肉を運ぶための竹かごを編む姿。寿は立派な体格でしたが、争いごとは嫌いで、優しい性格でした。そして、編み上げた竹かごには、父・山右衛門が使っていた「山」に「安」のマークを記しました。
昭和30年代に入ると、宇部市の精肉店から注文を受けるようになりました。朝6時ごろから正肉(骨や余分な脂肪をとった肉)を仕上げると、当時はまだ蒸気機関車だった岩徳線の貨車に積み込み、一路徳山へ。そこから山陽本線で宇部へ…。「山」に「安」の竹かごが、連日、周防高森と宇部を行き来していました。

▲岩徳線を走る蒸気機関車(昭和初期)
できそこないのハムの味
初代・寿と二代目・親之は安堂商店を軌道に乗せるために、さまざまな試行を繰り返しています。その一つに、ハムの製造がありました。
安堂商店を昭和22年に開業する前、マンガン鉱を九州の八幡製鉄所へ納める仕事をしていた時期があります。そのときに得た資金を元に、ハム・ソーセージの製造機械を手に入れました。それは徳山海軍燃料廠(ねんりょうしょう)からの払い下げ、ほとんど使われていない新品同然の設備でした。
その頃、安堂商店には新たな戦力が加わっています。親之の弟・安堂繁美(昭和6年~、1931年~)です。繁美は宇品引揚援護局(主に東南アジア各地からの引揚・復員を担当)に勤める公務員でしたが、父と兄が始めた家畜商に魅力を感じ、実家に戻っていました。
昭和24年、広島市から技術者を招くと、泊まり込みでの指導を受けて、ハムの製造が始まりました。目標は、1年前に創業して先を走る福留ハムです。その意気込みは、「山陽ハム加工」という新しい屋号を名乗ったことからもうかがい知ることができます。
昭和27年生まれの光明には、忘れられない味があります。それは、祖父と父、そして叔父が作ったハムの味です。うまくできたものはもちろん取引先へ卸します。だから、子どもの口に入るのはいつも、うまく固まらずにひび割れた不良品ばかり。それでも、おやつ代わりに食べたあの素朴な味わいが忘れられないと、光明は言います。
ハムの主流は豚肉ですが、安堂商店は牛肉で作っていました。つなぎに使っていたのはウサギの肉。だから当時は、ウサギの肉をいつも求めていたようです。先発の福留ハムが新商品を発売すると、その商品に似たものを製造するなど、家畜商や牛肉加工卸との兼業ですが、精力的な事業運営が続きました。
しかし、規模を拡張する専業メーカーとの競争には勝てませんでした。昭和30年に入ると、現在の日本ハム、伊藤ハム等も本格的な製造を開始しています。安堂商店はハム製造からの撤退を余儀なくされました。
ハムを作り始めてから約7年が経っていました。その間、親之は地域の農家と共に、肉牛の新しい肥育制度を考案し、軌道に乗せつつありました。一方、弟の繁美は乳牛の斡旋事業に目を付けていました。兄弟それぞれが違う方向から、安堂商店の屋台骨を作ろうと、動いていたのです。

兄:安堂 親之(二代目)

弟:安堂 繁美