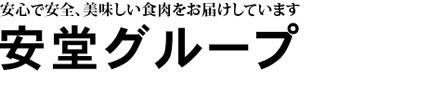安堂グループの歴史物語[第3話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第3話
若き兄弟それぞれの奮闘
終戦の混乱期を経て、昭和30年代に入ると、貧しかった日本人の食生活にも徐々に変化が訪れます。経済白書(昭和31年)には、「もはや戦後ではない」との言葉が躍りました。野菜や魚中心の食卓に肉やハム・ソーセージ。昭和39年には学校給食に牛乳が登場しました。
社会が大きく変わろうとしていたその頃、店主・寿のもとで頭角を現してきた二人の息子たちは、時代の一歩先を見据えていました。
兄・親之の画期的な牛の肥育方法
ハムをまだ製造していた昭和25年(1950)、24歳の二代目・親之は、地域の畜産業にとって画期的な制度を開始しました。それは、自ら牧場を持つことなく、農家に肉牛を大きく育ててもらうという「肉牛の預託制度」です。
安堂商店は、出産後の痩せた経産牛(子牛を生んだ母牛)を農家に提供し、農家の手によって育ててもらいます。農家が手塩にかけて牛を大きく育てると、安堂商店はそれを市場へ出荷。売上金から、預けた当初の牛の価格と手数料を差し引いて農家に渡しました。つまり、肥えた牛に育てるほど、農家の実入りは増えることになります。それはすなわち、安堂商店にとっても手数料が増えることを意味しました。
農家は餌や肥育環境の改良に進んで努力し、安堂商店もまた、より良い肥育方法の指導に尽力。時には契約農家を慰安旅行へ招待したこともあります。預託制度は、地域の農家にとっても、安堂商店にとってもお互いに利益につながる優れた制度だったのです。
やがて、この制度を地域の農協が取り入れることになると、親之は農協から依頼を受けて、そのノウハウを提供しました。そして、同業他社と共に、預託先農家への牛の斡旋と市場への出荷に精を出しました。その一方で、自らも牛の肥育をするようになりました。
農協の組織力により、肉牛の預託制度が地域に定着するにつれ、肉牛の生産量は増大し、安定しました。親之はその肉牛をせっせと市場へ出荷して忙しい毎日でしたが、ある問題に頭を悩ませていました。
競りの相場は一定ではありません。高値が付くときもあれば、極端に安いときもある。値が安定しないことは、農家にも安堂商店にも好ましいことではありません。しかも、出荷に係る手数料では利幅も少なく、かといって自ら育てる牛は数が知れている。そもそも、活牛(生きた牛)の扱いだけでは大きな利益を望むことは難しい。
悩める親之のところへある日、弟の繁美が妙案を持ちかけてきました。
「わしが、牛肉を販売してみようか」。

▲安堂商店牛舎(昭和30年代)
弟・繁美の小さな精肉店
ハム・ソーセージ事業の中心的な役割を果たしていた繁美は、事業からの撤退に少なからぬショックを受けていました。公務員の職を捨てて飛び込んだ実家の商売です。何とかして安堂商店を盛り立てたいという気持ちを、繁美は強くしていました。
市場へ出荷する牛を精肉にして自分で売れば、利幅がとれるし、客が付けば売り上げも安定する。持ち前の商魂に、再び火が灯りました。
昭和27年、繁美は光市にある製薬工場の正門近くに店舗を構えました。わずか一間(1.8m)の間口という小さな精肉店の出現に、地域の同業者は当初、気にも留めていませんでした。
ところが、ほどなくして繁美の店には客の行列ができるようになりました。そこは、市場へ牛を出荷する安堂商店の直営店です。「安くて新鮮」という評判が瞬く間に広がったのです。さらに、「新鮮」にはもう一つ理由がありました。繁美は知人を頼って店近くの製薬工場の巨大な冷蔵庫の一部を間借りしていました。当時、冷蔵庫を完備する店は地域にはなかったため、その効果は絶大でした。
ただ一つ、繁美の店には重大な弱みがありました。それは、肉を捌く知識と経験に乏しかったことです。ある日、外モモという部位を、通常はあり得ないステーキ肉として店頭に出したことがありました。外モモとは、高森地区では別名ケンビキ(腱引き)と呼ばれ、脚の腱を引っ張る筋肉です。部位のなかでも最も鍛えられたところだから、噛み切れないほど固い。それをステーキ肉だと言われて買わされた客はたまったものではありません。「こんなものが食べれるか!」と、激しく叱られたのも当然です。
しかし、それでも連日の行列が消えることはありませんでした。むしろ、客は増える一方でした。

▲昭和30年頃の解体方法「温体カット」
慌てたのは他の精肉店でした。ある老舗は一計を案じ、安堂商店から肉を仕入れたいと言ってきました。肉を仕入れてくれる得意先が同じ地域にできたとなれば、直営店で派手な商売をするわけにはいかなくなります。
安堂商店は老舗店からの注文を受けることにしました。直営店の売上を減らしても、より安定した卸先を増やした方が、長い目でみれば得になる。父と兄による賢明な判断でした。
そして繁美は、繁盛していた店を妹夫婦へ譲る決断を下します。「毎日、毎日、肉をさばいて、大勢の客を相手にするのにはもう、ほとほと疲れ果てた」と、繁美は笑っていましたが、それは半分は本音で半分は冗談。活牛を加工して販売する道筋が作れたのを見届けて、また新たな事業に商魂を燃やそうとしていました。
肉牛から乳牛へ
繁美にはある考えがありました。
昭和30年代に入り日本人の食生活が変化していくなか、乳製品への関心が高まりつつありました。しかし、乳製品の生産を国内で担っていたのは北海道などの一部の産地だけです。
「これからは全国各地で酪農が盛んになる」。そう時代を読んだ繁美は、早速行動に移しました。ホルスタイン種乳牛の産地・伊豆下田(静岡県)に出向き、獣医・下村甚之助と知り合うと、乳牛の仕入れに成功。それを皮切りに、地元山口県東部の農家へ乳牛を斡旋するビジネスを開始しました。
繁美の読みは見事に的中。乳牛への旺盛な需要を賄うため、時には北海道にまで足を運んで買い付け、鉄道貨物に載せて運びました。繁美自身も貨車に同乗し、牛の世話をしながら長旅に耐えたと言います。乳牛の斡旋先は広がり、東広島にも提供するようになりました。
繁美のこの働きは、地域に酪農が根付く一助になりました。そして、栄養満点の牛乳が、より身近なものになったのでした。

▲農家へ収めた乳牛(昭和30年代)
常に時代の一歩先を見越して、思い切って行動を起こす。これが安堂兄弟の真骨頂であり、安堂商店が躍進する原動力でした。肉牛の預託制度に始まり、自らも肉牛の肥育に乗り出した兄の親之。その肉牛を安定した収入源に変えたのは、行列のできる精肉店を作った弟の繁美。
兄はますます肉牛の生産と出荷、そして加工販売の分野を伸ばす一方で、弟は乳牛の普及に貢献する。両者はまるで両輪のように、時代の先へ先へ安堂商店を力強く前進させていました。
そんな安堂商店のところへある日、一人の男が訪ねてきました。後に繁盛店「いろり山賊」を開業することになるこの人物が、安堂商店の将来をさらに大きく変えることになろうとは…。
夕暮れ時、突然の訪問に対応した寿にはまだ、知る由もありませんでした。