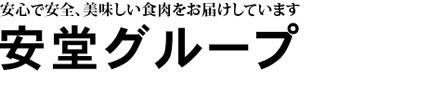安堂グループの歴史物語[第18話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第18話
「戦場と化した売場」
平成3年(1991)の輸入肉自由化を発端に肉牛の相場は暴落し、安堂畜産は一時的に大きな利益を得ました。その利益が新社屋建設を後押ししたことは、第17話に著したとおりです。
しかし、相場には損もつきもの。従業員50人の中堅企業になっていた安堂畜産にとって、予測のつかない相場の動きは、経営の安定を損なう心配の種でした。
ある社員との出会い
新社屋が完成する5年前の平成元年(1989)4月、安堂畜産はスーパー・こーべや玖珂店(現・肉のこーべや玖珂店)にテナントとして直営の精肉店をオープンさせています。直営店を持っていることは、肉牛の相場リスクを回避する有効な手段の一つです。肉牛の仕入れが高騰しても、直販のチャネルがあれば、その利幅のなかで吸収することができます。加えて、より付加価値の高い商品に加工することにより、高値での販売も可能になります。
実は昭和60年(1985)頃から、安堂畜産は食品スーパーへのテナントという形で出店を始めていました。光明にとってその取り組みは当初、さほど難しいことではないことのように思われました。食品スーパーとの取引を獲得するため、店頭でのより進んだ販売方法を研究していた光明は、販売員への指導を引き受けるようになっていたからです。例えば光明が考案した、生肉のスライスを三角に折って陳列する手法は、ボリューム感を作りながら、肉の発色を長持ちさせるものとして高い評価を得ていました。
しかし、社長自らが店頭に立つわけにはいきません。店を任せられる人材の獲得と育成が、ここ数年の課題でした。新規出店したスーパー・こーべや玖珂店も、店長を任せられる人材が定着せず、光明の頭を悩ませていました。
ある取引先の食品スーパーを訪れたとき、光明は浮かない顔をしている店員に声を掛けました。
「おうっ、どうかね。またゴルフにでも行こうやぁ」。
声をかけられて、一瞬、笑顔を見せた店員でしたが、いつものような楽しい会話にはなりません。
「新しい職場が、合わんかね」と光明。
店員は「いかにも…」という表情で苦笑いしました。
その店員とは、吉本里美(当時38)。スーパーの精肉部で長年、店頭に立って販売を仕切ってきた中堅社員です。女性のような名前ですが、面長のイイ男。商品知識はもちろん、丁寧で明るい接客で客からの信頼を得ていました。
ところが、会社の経営方針が変わり、それまで店頭で行っていた肉のスライスやパックの仕事は、工場で一括して行うことになり、技術に長けた吉本は、工場への配置転換になっていました。
「お客さんと会えないと…、どうも調子が出ないんです」。
それから数か月後のこと、スーパー・こーべや玖珂店の精肉店に吉本の姿がありました。店頭に立ちたいという希望が叶い、水を得た魚のように生き生きと働く吉本が、光明の目には眩しく映りました。そして、店にも慣れた師走の頃、あの伝説の出来事が起きてしまいました。

▲吉本里美さん(故人・2007年当時)
■伝説の出来事
年の瀬も迫った平成元年の12月29日、平成になって初めて迎える正月に、人々の心も浮足立ち、財布の紐も緩んでいました。日経平均株価は史上最高値を記録し、後から思えばその時、バブルの絶頂期を迎えていたといえます。
29日は「肉の日」です。正月用にいつもとは比較にならない量の肉が売れる年末に、「肉デー」と謳って大セールを打つことになっていました。吉本は、前に勤めていたスーパーでの経験を基に、販売予測を立てて、十分な量の商品を用意して当日を迎えていました。
「まあ、このくらいあれば、大丈夫。ひょっとして余ったら大変だな」。
吉本はゆったりした気持ちで朝を迎えていました。ところが…。
開店して1時間ほど経った朝10時、光明へ電話がありました。声の主は吉本です。
「あの…、もう、ダメです」。
事故でも起きたかと驚いて問いただす光明に、吉本は、
「お客さんが、入りすぎです! 早く補充をお願いします」。
用意していた商品がなくなれば、予備を店頭でスライスして間に合わせながら、本社からの供給を待つしかありません。店頭はお昼を前にして戦場の忙しさ。精肉コーナーに並ぶ客は店内を1周して、お店の外にまで列を作っていました。店員たちも必死なら、肉をスライスする機械(スライサー)もフル稼働。お昼を過ぎる頃にはとうとう、スライサーから白い煙が上がってしまうという、前代未聞の状況でした。
その日の売り上げを集計してみると、1千万円を超えていました。
「あんなにお客が来るとは…」。吉本はただただ驚くばかりでした。

▲肉デーの店頭(肉のこーべや玖珂店・2007年)

▲店の外にも並ぶお客様(肉のこーべや玖珂店・2008年)
その後、光明と吉本のコンビは、各地のスーパーへの出店を実現していきます。出店の都度、二人は、その地域性や店の特徴を話し合い、作戦を練ります。光明が様々な卸先で見聞きして編み出したノウハウと、吉本の実践で培った技術が相乗効果を発揮していきます。
平成5年(1993)には、スーパー・こーべや玖珂店は、安堂畜産が店全体を運営することになり、肉の売場が4分の1を占めるという異色のスーパー、「肉のこーべや」が誕生しました。
毎月29日には、「肉デー」を開催。行列のできる肉屋として、県内外から顧客が訪れます。もちろん、商品を切らすことも、スライサーが煙を吐くことも、その後は一度もありませんでした。
新たな要求
平成5年(1993)は、安堂畜産にとって節目の年になりました。新社屋による加工の合理化と生産力の増強、チャーター便による流通網の拡充、そして、「肉のこーべや」に代表される直営店の成功など…。
そんな前のめりになっている光明の元に、また新たな要求が、山口中央生協(現・コープやまぐち)から降りかかってきました。
「組合員(お客様)に供給する肉を、山口県産に限定したい」。
いわゆる地産地消の流れです。自社牧場はあっても、それだけではとても足らず、生協に供給する牛肉の多くは、全国の市場から調達した肉牛のものでした。
父・親之により整備された牧場、そして光明により拡大した取引や流通の拡充。そして再び肉牛の肥育に力を入れなければならない。終わることのない投資のループ。それは、新たな時代へ昇る螺旋階段でもあることを、光明は感じ取っていました。