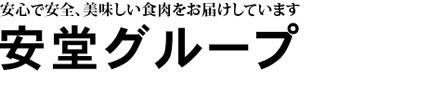安堂グループの歴史物語[アナザーストーリー 1]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
アナザーストーリー 1
「顧客のニーズが成長の種」
事業の開発と発展には、二つのアプローチがあります。
一つは、それまでになかった画期的な発明や商品開発により、新たな市場を開拓するアプローチ(以下、発明型)です。例えば、ソニーのウォークマンやアップルのiPhone等。失敗のリスクも大きければ、成功したときの有形無形の利益は計り知れません。
もう一つは、市場のニーズにいち早く対応し、商品・サービスの進化を図るアプローチ(以下、ニーズ対応型)です。こちらの手法では、一気に莫大な利益を得ることは難しいでしょう。しかし、失敗したときのリスクは少なくて済みます。うまくことが運べば、既存の顧客に喜んでいただきながら評判を得て取引は確実に拡大します。安堂グループはまさしく、このアプローチにより発展を遂げてきました。
発明型はとても難しくて、天才肌のアプローチです。対してニーズ対応型は比較的易しくて努力家のアプローチのように思えます。ところが、ニーズ対応型で成功するためには、リスクを承知で果敢に挑戦するアグレッシブな態度が、実はキーになるのです。
部位別(パーツ)卸売りの開発
昭和50年(1975)、大学で獣医師資格を得て安堂商店(現・安堂グループ)へ入社した安堂光明(3代目社長、現・会長)は、父・親之(2代目社長)に代わって家畜市場の競りに出るなど、商売のイロハを学びはじめます(第10話「光明の試練」)。同時に、親之の指示に従って、販売先の開拓にも奔走するようになりました。
昭和50年代半ばになると、各地にスーパーマーケットが台頭。食品販売の主役は、街の小店からスーパーへと変わっていきました。安堂商店はスーパーとの取引を拡大し、取引先は山口県内はもとより広島県にも及ぶようになりました。
競合する他社を差し置いて、なぜ安堂商店が躍進を遂げることができたのか。それは、スーパーの店長らが口にした要望や不満をニーズとしてキャッチし、それに応えるために果敢に事業の改革に乗り出したからです(第11話「ちょっと行ってこい」)。
一頭や半頭を丸ごと売ろうとするその頃の畜産業者の思惑に対して、スーパーが望んでいたことは違っていました。
「うちの前身は八百屋だからね。大きな肉の塊を持って来られても、さばけないよね」。
スーパーのほとんどが、スライスするだけで店頭に並べられるような各部位に切り分けてある肉を仕入れたがっていました。しかも、できれば売れ筋の部位がたくさん欲しい。
光明は部位別の卸売を実現するため、畑違いの豚肉加工業者の門を叩きました。牛肉での部位別販売の事例が地域にはなく、全国でも稀だったからです。しかし、この奇想天外な行動が功を奏することになります。部位別の流通を教えてくれたある豚肉加工業者では、豚肉を単に部位別に分けることに止まらず、顧客のニーズを汲んで、ステーキ用や焼き肉用など肉塊を切り出せばすぐに陳列できる用途別の商品を開発していたのです。
昭和55年(1980)、光明は牛肉の部位別・用途別の卸売をスタートさせています。翌年には、生肉の消費期限を劇的に伸ばす真空パックの技術を、地域の畜産業者に先駆けて導入しています(第12話「安堂のため、地域のため」)。
競合他社にも、スーパーからの同様の要望は届いていたはずです。そして、これを実現することが容易ではないこともまた、周知のことでした。そんななか、光明はその困難を避けて通ろうとはしませんでした。難しい問題であればあるほど、「何か解決策はないだろうか」と考えを巡らせて試行する。そんな前向きな態度は、安堂家の気性だと言っていいでしょう。
小さな工夫、大きな成果
さて、スーパーにマッチした部位別・用途別の商品開発に成功したからと言って、手放しで取引が増えるほど商売は甘くありません。そこには、スーパーの事業に関わる人たちとの出会いが欠かせませんでした。卸先のスーパーで知り合った精肉販売のコンサルタントとの出会いも、その一つでした。
あるとき、光明はスーパーの店頭にいました。自らが納品した精肉の陳列を確認していたとき、ある商品に目がとまりました。それはどこの店頭にもある「こま切れ」です。自分が卸した肉ですから、肉そのものに驚きはしません。目が釘付けになったのは、その盛り方です。
普通なら、「こま切れ」をトレーに敷き詰めて、ケースに入れてあるだけです。すき焼き用やステーキ用と並んで、いかにも安くて沢山買える。そんなイメージです。
しかし、ここの盛り方は違います。「こま切れ」一枚一枚がふっくらと軽く盛られていて、それはまるで炊き立てのご飯が茶碗に盛られているようにふわっと山盛りになって、その一山一山がいかにも美味しそうなのです。
顔を上げて、作業場を見ると、まさに盛り付けているところでした。スライサーから切り出されてくるスライスを手の平さいずにふわっと立てるように重ねます。隙間にできるだけ空間をつくり空気を含ませているような感じです。
「そうか、肉同士が触れると変色するが、あのやり方なら、空気が入って変色が防げるし、量感も増す」。
店員に聞いてみると、その盛り方は精肉販売のコンサルタントから教えてもらったとのこと。光明はそのコンサルタントと名刺交換をして、帰路に就きました。
その日の夜のこと、光明は食事を終えた食卓で、何やらつぶやき始めました。
「こうかのぉ…。いや、ちょっと待てよ、こうの方がええかのぉ」。
何をしているのかと、妻の朱美が覗いてみると、光明はティッシュを折っています。
「何をしてるいかって? スライスの折り方を考えよるんよ。どうやったらふわっとこう、美味しそうにみえるか…」。
光明は「こま切れ」の盛り方を参考にして、スライス肉の新しい陳列方法を編み出そうとしていました。できるだけお皿との接地面や肉同士が触れることも少なくて、ふわっとして量感も出せるように…。こうして考案されたのが、スライス肉を軽く畳んで三角形に立てるような折り方でした。
さっそく、当時展開していた精肉店のFC店に指導し、これによって店頭の売り上げを増やすことに成功しました。そして、その折り方の噂を聞きつけたコンサルタントたちが、店に視察に訪れるようになったのです。

▲安堂光明が精肉の陳列方法を考案するきっかけになった「こま切れ」の陳列。(肉のこーべや玖珂店)

▲安堂光明が編み出したスライス肉の陳列方法(肉のこーべや玖珂店)
ニーズのその先へ
さらにコンサルタントとの出会いは、思わぬ展開をもたらしました。コンサルタントから取引先の紹介を受けるようになったのです。というのもコンサルタントは、スーパーのニーズに対応してくれるような卸売業者を、ずっと探していました。
安堂商店は、当時稀だった部位別の牛肉を取り扱っていました。しかも、店頭でスライスすればすぐに陳列できる用途別に切り分けた商品です。さらには昭和56年(1982)には既にミニスーパーのために、そのまま店頭に陳列できるパック済みの商品まで開発。その翌年にはこれを生協に納入する体制を確立していました。まさしく安堂商店は、コンサルタントのクライアントに喜ばれる仕入れ先だったのです。
その後、同様のコンサルタントとたくさん知り合うようになると、それらの紹介を得て安堂商店の取引先は飛躍的に増えました。また、鶏肉の卸売業者等、同業者からも一緒に納品しないかという引き合いも受けるようになりました。こうして、取引先は、山口県内はもちろん広島県にまで拡大したのです。
【スーパーからの要望から生まれたパック済み商品】


▲SMP(スライス・ミート・パック)は、スーパーのバックヤードで小分けして陳列する商品。


▲GP(グループ・パック)は、そのまま店頭に陳列できる小分け済みの商品。
安堂グループにとって、取引先からの要望は事業発展のための「種」です。それがたとえ苦情であっても、それら一つひとつから逃げることなく対処していくことこそが、社会貢献にもつながります。生協から「パックに虫が入っていた」との苦情から、窓のない工場を新設したのもその一つでした(第17話「虫と新社屋の関係性」)。
さらには、「食の安全」という、社会全体からの要請について、安堂グループは早くから対応をしてきました。
次回には、その取り組みについてのアナザーストーリーをお伝えすることにします。